たしかに、悲しい別れだったのかもしれない。
でも、あの微笑みの奥に、ほんのわずかな“まだ続く何か”を感じた気がした──。
「薬屋のひとりごと」第46話「禁軍」は、数多くの謎が明かされる回でもありました。
その中で、とりわけ強く心を揺らしたのは、子翠という人物が辿り着いた静かな結末です。
後宮に仕える一人の侍女として振る舞いながら、実は楼蘭妃という過去を背負い、
さらには“子の一族”の未来をも握る者であった子翠。
彼女が見せた最期──いや、“最期のように見えた”あの場面の、その奥にあるもの。
今日は、46話の衝撃とともに、原作でそっと示されていた「もうひとつの真相」について、
声をひそめるように語ってみたいと思います。
子翠=楼蘭妃、その静かな正体に触れて
あの人が、ただの“下女”ではない気がしたのは、いつからだっただろう。
視線の流し方。足音の軽さ。虫を手に取る指先に、どこか“訓練された匂い”があった。
けれどそれは、猫猫の目をもすり抜けるほど自然で、違和感よりも“違和感のなさ”に紛れていた。
第46話で明かされた衝撃──子翠は、かつて後宮に名を馳せた楼蘭妃だった。
淑妃の座にありながら、自ら宮廷を離れ、別の人生を歩み出した者。
いや、それは「逃げた」のではなく、「潜った」のだ。
子の一族という、王権の記憶にとって都合の悪い血筋。
その存在を見張るため、あるいは、彼女自身が“最後の処理者”となるために。
そのために彼女は、名前を捨て、身分を捨て、笑みを偽り、虫を語った。
侍女という仮面の下で生きる日々。
それはきっと、誰よりも自由でなく、誰よりも孤独だった。
でもそれでも、あの人のまなざしは澄んでいた。
たとえそれが、最後の役目を果たす者の、澄んだ諦念だったとしても──。
簪と「虫なら冬を越せた」の余韻
冬を越せる虫と、越せない虫がいる。
その違いは、強さではなく、ほんの少しの運と、ほんの少しの場所。
たとえば土の中。たとえば人の懐。あるいは──偶然、かんざしが守ってくれた心臓の裏。
砦の上、銃声とともに彼女の身体が宙を舞った瞬間、
世界はすべてが終わったかのように静かだった。
猫猫が託した簪。それはただの贈り物ではなかった。
無骨で不格好なそれが、弾丸の軌道を逸らす「盾」となり、命を繋いだ。
でも、そんな奇跡すら──彼女は口にしなかった。
ただ一言、
「虫なら、冬を越せたのに」と、ほほ笑んで。
それは“死”を覚悟した者の諦念だったのか、
それとも、“生き延びる”側へ託された祈りだったのか。
どちらにせよ、その言葉はまるで、
彼女自身が虫になって、冬を越えていこうとしているように聞こえた。
こちらの記事もおすすめ
アニメでは“死”、原作では“生”の可能性
アニメ第46話「禁軍」では、子翠の命は“終わった”とされる。
砦の壁から転落し、血の海に沈んだその姿。
彼女を撃った兵士の手は震えていて、猫猫の目は、どこか遠くを見つめていた。
それは誰が見ても、幕引きのように整えられた“死”だった。
だが──
原作を読む者には、そこで終わらない気配が残されている。
銃弾の軌道、簪の硬さ、そして死体が回収されたという描写のなさ。
さらに、数章後には“玉藻”と名乗る女が港町に現れ、簪を売る場面がそっと描かれる。
虫を語り、飄々として、でもどこか名残惜しげに微笑む彼女。
あの人が、あの場所で終わる人ではなかったと知っている私たちには、その姿がまぎれもない“答え”に見えた。
だからこそ、アニメが描いた“死”は、
原作が残した“生”と、まるで二重写しのように重なっていく。
物語の表面では静かに葬られた者が、
読者や視聴者の“記憶の奥”では、なお生き続けている──。
“玉藻”という名前に託したもの
名前を変えるということは、過去を脱ぎ捨てることだ。
でも、“玉藻”という名には、不思議と棘がなかった。
それは新しい皮膚のようでいて、どこか柔らかく、すこしだけ懐かしい響きがあった。
楼蘭妃でも、子翠でもなく、ただ一人の女として生きるための名。
かつて彼女は、宮廷の装束に身を包み、子の一族としての重荷を背負っていた。
そして次には、侍女として身分を偽り、宮廷を内側から観察し続けていた。
でも“玉藻”の彼女は、もう誰のためにも微笑んでいない。
宝石商に簪を売り、遠くを見る目にあるのは、計算でも策略でもない。
ただ、次の季節を迎えにゆく人の目だった。
虫たちが越冬するように、名を変えて、棲みかを変えて、
彼女は彼女だけの春を迎えようとしていたのだろう。
“玉藻”という名は──
役目を終えた者が、もう一度“ただのひとり”に還るための名前だったのかもしれない。
別れのあとに続く物語
たしかに、あれは別れだった。
猫猫は砦に残された記憶と向き合い、
壬氏は剣を手に軍を率いてゆく。
そして、子翠は“死んだ”とされる。
物語は静かに、それぞれの登場人物を次の章へと送り出していった。
でも、玉藻という存在は、それだけでは終わらなかった。
その後、港町で簪を売る彼女の姿を目にした誰かは、
「人形みたいな娘だった」と、どこか懐かしむように語る。
そこに猫猫の姿はない。
再会は描かれない。呼びかけも、手紙も、微笑みも、交わされない。
けれど──
別れのあとに、こんなふうに物語が“つづいていた”こと。
それ自体が、再会とは別のやさしい奇跡だったように思う。
人が人として生きていくには、「名前」が必要だ。
でも人が人にとって記憶になるとき、それは“名を越えた何か”に変わっていく。
子翠の名を知る人がいなくても、“玉藻”の暮らしのどこかに、
猫猫との時間は、きっと棲みつづけている。
おわりに──終わらなかった人
「死んだ」と聞かされたとき、私たちはその物語を閉じてしまう。
でも、本当に終わった物語には、“あの微笑み”は残らない。
子翠──いや、玉藻と名を変えた彼女が今、どこでどんな風に生きているのか、
それはもう、物語の中でも描かれない。
けれど私は思うのです。
あの港町の風のなか、今日も簪を髪に挿して、
虫の羽音に耳をすませている女性が、たしかにいるような気がして。
たしかに別れだった。
でも、それが“終わり”とは、どうしても思えなかった。
終わらなかった人──
それは、名前を残さず、声も残さず、それでも誰かの心に住み続ける人。
物語を読んだ後、その人の姿が、記憶の片隅にずっと佇んでいるような──
そんな静かな奇跡を、私は子翠という女性に感じています。

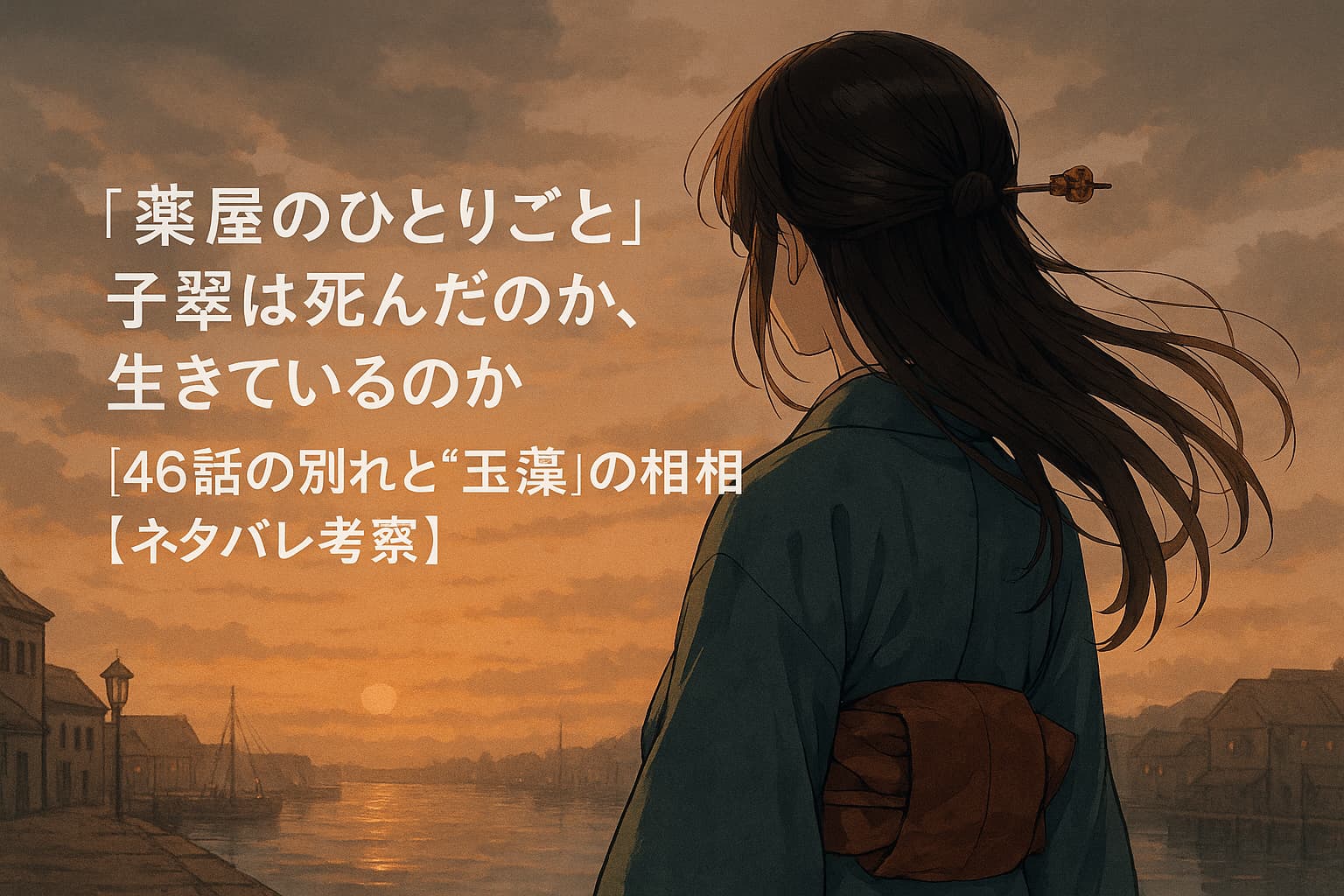


コメント